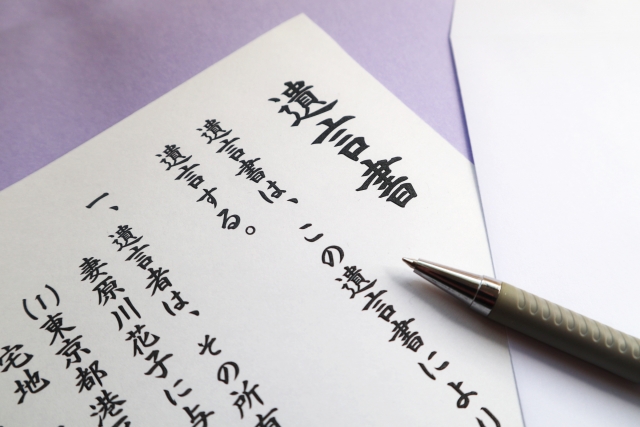
終活の中でも最もポピュラーなのが遺言書です。
遺言書なんて自分には必要ないと思われる方も多いかもしれませんが
遺言書を書く意味が無い方の方が少ないかもしれません。
人の寿命は神様ぞ知る…です。
今お元気であっても、極端な話、明日何があるかわかりません。
お元気な内に遺言書を作成し、安心して過ごしましょう。
作成した後にお気持ちが変わったらまた書き直せば良いのです。
特に遺言書を書いておくべき人
資産が多い
当然、多ければ多いほど相続人間で揉める可能性が高まります。それまで仲の良かったご家族がご自身の死後、ぎくしゃくしたり、いがみ合ったりするのは悲しいですよね…
遺言書を作成しておくことで余計なもめ事から残されたご家族を守る事につながります。
不動産がある
「うちは不動産しかないから」と仰る方がいますが、不動産があるからこそ、遺言書を作成するメリットがあります。
死後、不動産は相続登記をする事になりますが、遺言書が無い場合には相続人や被相続人の戸籍集め、財産目録の作成等必要な書類収集をして、そこから遺産分割協議をします。話し合いです。この「話し合い」が一番やっかいでもめ事の種です。
話し合いがまとまればようやく遺産分割協議書を作成(専門家に依頼する事が多い)し、登記手続きに移行していきます。
ご家族である相続人が全てこの流れをする事になります。もしくは専門家に依頼する事になる訳です。
遺言書があれば、遺産分割協議書を作る必要が無いのです。ですから話し合いもいりません。
相続登記手続きがあっという間に完了出来ます。
ご自身が亡くなった後のご家族のご負担を考えますと、遺言書を作っておいて差し上げるのが望ましいのです。
相続人以外の方に資産をあげたい方
例えば、自分の介護を一生懸命してくれた長男のお嫁さんであるとか、もしくはお孫さんなど、相続人ではない方に資産をあげたい場合には、遺言書が必須になります。
財産承継の文言に併せて、付言でその方への感謝の気持ちなどを記載する事も出来、相続人への理解を求める事も出来ます。
お子様のいない夫婦
お子様のいないご夫婦ですと、夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者が全て相続できるわけではありません。亡くなられた方の親御様がもしご健在なら親御様と、兄弟がいれば兄弟と法定相続分で分け合う事になります。
この場合、遺言書が無ければ配偶者は義理の親、もしくは義理の兄弟と協議をする事になります。遠慮して思っている事が言えない事もあるかもしれません。
兄弟が亡くなっていればその子供である義理の甥や姪と協議をしなければなりません。会った事も無いかもしれません。
いずれにしても既に高齢になっているかもしれない配偶者の精神的負担がとても大きくなってしまいます。
遺言書があれば協議も必要ありません。遺言書に沿って手続きをすれば良いだけです。
配偶者に遺産のほとんどをあげたいと思われているのであれば遺言書にその旨を残して配偶者の負担を軽くしてあげましょう。(遺留分については考慮しておかないと、結局後にもめる可能性を残してしまいますのd絵その点注意が必要です)
子供がいる夫婦だったが離婚、その後に再婚した方
例えばAとBが結婚して子供(C)が生まれました。
その後離婚をしてCのことはAが引き取り、BはDさんと再婚して子供(E)が出来ました、という場合。
Bが亡くなるとCとD、Eが相続人となる訳です。「前の奥さんや子供とは離婚してから会っていない」という方も多いかと思いますが、その場合、CはDやEと会ったことが無く、存在すら知らなかった、Bさんが死んで初めて知ったという事もあります。
そんな中での遺産分割協議をしなければいけないのです。
また、離婚後はAと一切連絡を取っておらず、連絡先も分からないという場合には、相続手続きの為に探す必要があります。探して、見つけたら事情を伝え、そこからの遺産分割協議です。
会った事もない人といきなり財産の分け方について話し合う訳ですから円満にいかない事は多々あります。
ご自身が遺言書を残しておけば、皆にとって心的負担になってしまう色々な経緯や遺産分割協議が必要なくなります。
結婚した相手に連れ子がいる場合
結婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ自分の子供という扱いにはなりませんので、相続人にはなりません。結婚相手の連れ子にも財産を承継させたいのであれば養子縁組をしておくか、遺言書でその子供へ遺贈する旨を記載しておく必要があります。
事実婚の場合(内縁の妻、夫がいる場合)
内縁の妻や夫は法的には相続人になりませんので、そのパートナーに資産を承継したいのであれば入籍をするか、遺言書で遺贈する旨記載する必要があります。
身寄りの無いおひとり様
相続人がいない方が亡くなり、特別縁故者もいないという事になれば相続財産は国庫に帰属します。生きてきた中で作り上げてきた資産ですから、亡き後の自分の試算はお世話になった方に遺贈したり、慈善団体に寄付する、といった事を検討する方もいらっしゃいます。そういった場合には遺言書が必須です。
他の制度と遺言書の併用
終活と一言で言っても、ご本人の要望に合わせて色々な制度を検討する事が出来ます。
認知症対策としては家族信託や任意後見など、死後の対策としては死後事務委任があります。
これらの任意後見や死後事務委任契約を選択する時に公正証書遺言書の作成を併せて検討してみると良いパターンがあります。
①任意後見契約と遺言
任意後見契約とは、ご自身がまだ元気なうちに信頼の出来る相手を後見人に選んで、認知症になってしまった時の財産管理や身上監護の手続きなどをやってもらう契約です。
この契約は厳重な本人確認が必要なため、必ず公証役場で公正証書にする必要があります。
直接的に遺言書が任意後見に関わってくるわけではありませんが、せっかく任意後見契約で公証役場に行くのであれば、一緒に公正証書遺言を作ってしまうと良いかもしれません。一度の手間で2つの公正証書が作れます。(公証役場の費用はそれぞれかかります)
同じ専門家に依頼するのがポイントです。そうすれば何度も公証役場に行かなくても、任意後見契約と遺言の調印の日を一日で済ませる事も出来ますし、遺言書作成に必要になる財産目録も、任意後見契約で作成しますので、それをほぼ流用出来て手間がかなり省けます。
また、士業などの専門家に依頼する場合、セットで依頼すると報酬が安く設定されている事もありますので、費用面でもメリットがあります。
➁死後事務委任契約書と遺言+遺言執行
自身の死後の事務(葬式や家の明け渡し、埋葬や税金の支払いなど)をしてくれる家族がいないいわゆる「おひとり様」や子供のいない「おふたり様」が専門家に死後事務を依頼する死後事務委任契約というものがあります。
自分の死後の色々な手続きを、元気なうちに専門家などに依頼しておける死後事務委任ですが、家族がいない、もしくは家族が高齢の配偶者しかいないといった場合、実は死後事務委任契約だけでは不十分なのです。
死後事務委任では財産の承継(相続など)や身分に関する事(遺言執行者の指定など)は委任事項に出来ません。逆に遺言書では亡くなった後の葬儀などの死後事務を委任する事は出来ません。
ですから、死後事務委任契約と遺言書がお互いに足りない部分を補い合ってより安心できる対策といえるのです。
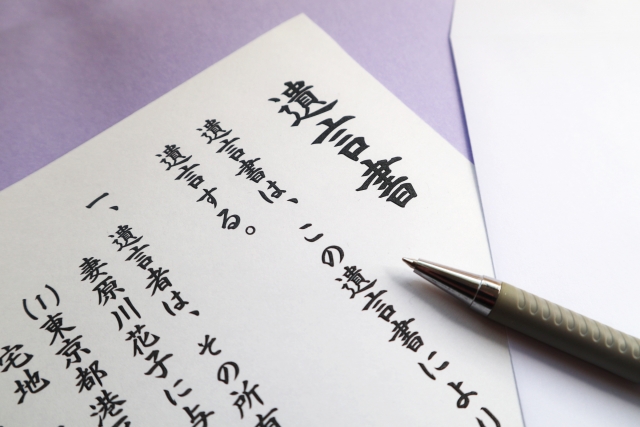
遺言書で
財産の承継
(例・土地や不動産、預貯金などの承継)
身分行為
(例・認知や遺言執行者の指定など)

死後事務委任契約で
遺体の引き取り 葬式や火葬
納骨や墓じまい
保険や年金などの手続き
家の退去手続き など
更に遺言書で死後事務委任契約の受任者を「遺言執行者」に指定しておくと、死後事務委任契約の執行費用を相続財産から差し引きする事が出来るので、契約時の金銭的負担が少なくなったり(受任者によって違いますが当事務所はそのような形が取れます)、そのまま死後事務と相続の承継を全て同じ人にやってもらえるので相談も一度で済み、手続きもスムーズになります。
当事務所におきましは、お元気なうちの遺言書作成、財産管理契約、みまもり契約、認知症発症後の任意後見契約、その他家族信託や亡くなられた後の死後事務、遺言執行まで、終活にかかわる色々な制度についてのご相談とご依頼をお受けいたしております。
遺言書と併せて他の制度を検討したほうが良いのか、こんな希望があるけれど遺言書だけでは足りないのか?などお気軽にご相談下さい。
遺言書の種類
自筆証書遺言
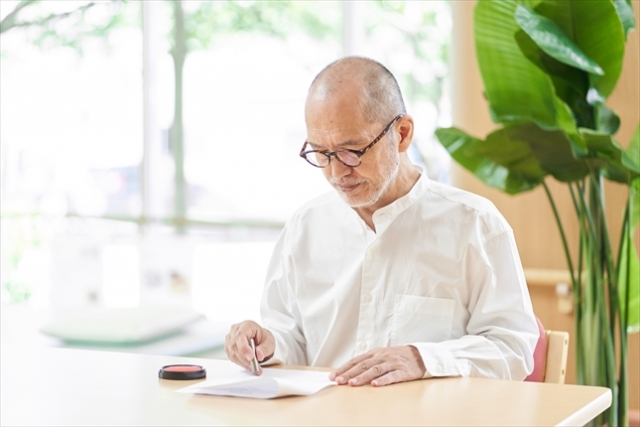
ご自身で作成し、ご自身で保管する遺言書です。
自筆証書遺言のメリット
・費用がかからない
・作り直すのも手間がかからない
自筆証書遺言のデメリット
・形式や内容(法的に)不備があると、せっかく残しても無効になってしまう可能性がある
・死後に発見してもらえない可能性がある
・遺言書は遺言者の手元で保管されるため、破棄されたり書き換えられてしまう可能性もある
・死後、遺言書が見つかっても勝手に遺言書を開く事は出来ず、裁判所での検認手続きが必要となるので手間や時間がかかる
この保管制度を利用すると形式さえクリアすれば法務局で遺言書を保管しておいてもらえるので
破棄や書き換えの心配がなくなります。
また、家庭裁判所での検認も必要なくなるため、自筆証書遺言のデメリットがいくつかクリアできる事になります。
公正証書遺言
公証役場で公証人が公正証書遺言として作成し、公証役場で保管してもらえる遺言です。
公正証書遺言のメリット
・公証人のもとで作成されるため、形式的な要件はもちろん、内容についても法的に問題ないかチェックしてくれますので、様式や内容の点で無効になってしまう心配がありません。
・原本は公証役場に保管されているので破棄や紛失の心配がなくなります。
・上記同様、原本は公証役場に保管されているので遺言書の書き換えや偽造の心配がなくなります。
・病気などで字が書けない状態であっても作成が可能です。(手配をする事で公証人が病院に出向いてくれますが認知機能がしっかりしているかの確認があります。)
公正証書遺言のデメリット
・公証役場に出向く必要がありますので(打ち合わせ、調印など2回以上出向く事になります)手間がかかります。
・行政書士や司法書士、弁護士に依頼した場合にはその専門家の依頼費用と公証役場の費用がそれぞれかかり、それなりの費用がかかります。
・証人が2名必要になります。これは身内(相続人にあたる人)は証人になれないので、それ以外の人で探す必要があります。
当事務所におきましてご依頼をお受けした場合、当職が公証人との打ち合わせなどについても全て行わせて頂きますので、ご依頼者様が公証役場に行くのは最後の調印の日のみとなります。(公証人の先生がご本人の判断能力に問題がないか判断し、読み上げる内容に間違いがないですか?といった確認をするだけですので然程時間もかかりません)
お体が悪くて公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人の先生に出張して頂けるよう当職が手配いたします。
また証人についても、当職が証人として調印に立ち合い、またもう1名も当事務所で行政書士等手配する事が可能ですので、ご依頼者様が探す必要はございません。
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言のデメリットをいくつか解決してくれる自筆証書遺言保管制度、これがあればわざわざ費用をかけて公正証書にする必要が無いのでは?と思われるかもしれません。
費用面でも自筆証書遺言保管制度のほうが安く済みます。
では公正証書にした方が良い一番の理由は何かというと、「無効にならない確実な遺言書」が作れる、という点です。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合、法務局に提出する時に法務局がチェックしてくれます。チェックして預かってくれたから安心だ…と思いたいところではあるのですが、このチェックというのは、様式を満たしているかどうか、という点だけで、書いてある内容についての適法性などについてはチェックされていません。
ですから万が一、内容が法的に問題のある内容が含まれいると、死後にこの遺言書の内容では無効だ…となってしまう可能性もある訳です。。
その問題点を解決できる遺言書が公正証書遺言という事になります。
公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命した人ですから法律のプロ中のプロです。
ですから、公証人が内容をチェックして問題無ければ中身についても完璧に問題の無い遺言書が出来上がる訳です。
そこまで考えなきゃいけないの?と思われるかもしれませんが、遺言を残す方は意図があって残す訳です。その意図が自分の死後、「無効」になってしまったら悲しいですよね。
作る以上は確実に、様式も内容も問題の無い遺言書を作りましょう。
またご病気で入院されていたり、お体が悪くて公証役場に出向く事が出来ない、という方であっても公証人に出張してもらう事も出来ます。
またご自身で文字が書けない状態であっても、ご本人の口述をもとに、それを聞いて公証人の先生が公正証書遺言を作成してくれますのでご病気でも安心です。
入院中や施設に入っていらっしゃる方、また手が不自由で文字が書けない方は自筆証書遺言保管制度を使うのが難しくなりますから、必然的に公正証書遺言を選択することになるかと思います。
当事務所におきましても、公正証書遺言に残す案文のアドバイスや作成、公証人との打合せや証人としての立ち合いなどトータル的にサポートさせて頂いております。
お気軽にご相談下さい。
尊厳死宣言書
最近では医療が高度になり、脳死状態(いわゆる植物状態)になっても色々な措置を施す事によって生きながらえる事が出来る時代です。
ですが、そのような状態になって更に高額な費用をかけてまで生きていたくない、と思われる方も少なくありません。
終末期といわれる時期に、回復の見込みがない状態になったら延命治療はせず自己の尊厳をもって旅立ちたい、というのが「尊厳死」といわれるものです。
この尊厳死を希望しているか否かは表示しなければ周りには分かりません。
お体が悪くなり、意識が無くなってしまったり、判断能力が亡くなってしまって意思表示が出来なくなってからですと自分でそれを伝える事出来なくなりますので、その前に「延命治療はしません」という意思表示を残しておく必要があります。この意思表示が尊厳死宣言書というものになります。
この意思表示を残しておくことで医療現場での治療方針の指針にしてもらえる可能性が高くなりますし、もし医師からご家族が延命治療について尋ねられた時にも、ご本人のはっきりとした意思表示が残っている事で、ご家族の一存で苦渋の決断もする事もなくなります。
そしてこの「意思表示」、遺言書ではだめなのです。
遺言書は遺産を死後どのように承継させるかという事を記載するものです。
「死後」です。
ですから、希望を伝えるという意味合いで書いていけない訳ではありませんが、亡くなる前の治療方針についての希望を医師や家族に伝えるには不向きです。そもそも生前に遺言書を開けて中を見る、ということは普通はしませんから遺言書に書いたところで無意味になってしまう可能性もあります。
そこで「尊厳死宣言書」を作成する事になります。「尊厳死宣言公正証書」とも言います。
尊厳死についてのご自身の希望を公証役場で公正証書にします。
公正証書にしておくことで確実にご本人の意思で作成された書面としての証拠能力を持ちます。
医療現場でこの尊厳死宣言書の確認がされた場合、法的拘束力を持つわけではありませんが、実際現場ではかなりの割合で尊厳死宣言書の意向に沿った対応がされているようです。
尊厳死宣言書に書く内容
・延命治療を望まないこと
・延命治療をやめる条件
・医師や医療関係者への免責事項など
当事務所におきまして、尊厳死宣言書作成についてサポートさせて頂いております。
・ご自宅への出張によるご相談、打ち合わせ
・尊厳死宣言書案文作成
・公証人との打合せ、日程調整
※調印当日、お体が悪い場合には当事務所の車にて公証役場まで送り迎えも可能です。
- 尊厳死と安楽死の違いはなんですか?
-
尊厳死は本人の希望で延命措置をせず、自然に死を迎えることです。一方安楽死は、医師など第三者が薬などを使用して死期を早める事です。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に依頼した場合にはその費用と公証役場の公証人手数料がかかります。公証役場の費用は11,000円+正本代1,000円で12,000円ほどです。
公証人の出張を依頼した場合には基本手数料11,000円×1.5、+日当(一日20,000円・半日10,000円)+交通費がかかります。
当事務所の尊厳死宣言書作成サポートのご依頼は22,000円となります。公証役場の車での送り迎えがありの場合には25,000円となります。
エンディングノート
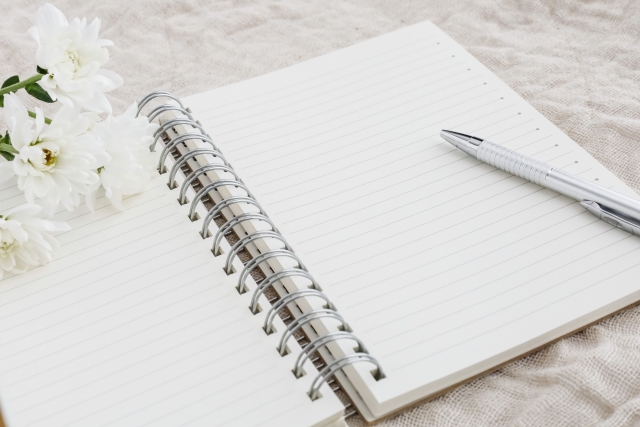
昨今よく耳にする「エンディングノート」
終活という言葉が一般的になったと同時にエンディングノートという言葉もよく聞くようになりました。
エンディングノートと遺言書は基本的には違うものです。
※書くことで遺言書としての要件を満たす可能性があるエンディングノートも中にはあります。
エンディングノートってそもそもどんなものでしょう。
終活をしていくにあたって作成する記録帳のようなものと考えるとイメージしやすいかもしれません。
そして遺言書は記載している事はすべて亡くなった後に効果を発揮しますが、エンディングノートに関しては一概にそうとも言えません。
ご自分で意思表示が出来なくなってしまった時にも効果を発揮する事があります。
資産についての記録
ご自身の資産状況(不動産や銀行の口座番号等)や通帳等がおいてある場所、金庫にしまっているのであれば開くためのカギの場所や番号などです。介護・医療の希望を書き記しておくことにより、亡くなられた後に相続財産がどこにあったのか、どんなものがあるのか、と探すご家族の手間(これが実はかなり大変な手間だったりします)が無くなります。
医療、介護についての希望
今後認知症になってしまってご自身で希望を伝えられなくなった時のために、自宅介護を望むのか、もしくは施設に入りたいのか(既に申し込みしているなど)、病気になった時の延命治療を望むのか、余命宣告を望むのか、といった事を記載しておくことでご本人も安心できますし、ご家族もご本人が意思表示できなくなっても意思を汲むことが出来ます。
ご自分が危篤状態または亡くなった際に連絡を取りたい方のリスト
ご家族以外にも危篤を伝えたい、亡くなった時にお葬式にきてほしい、という希望がある事もあるでしょう、そういった場合にはその方々のリストを作り、連絡先を記載しておくことで、家族が連絡をしてくれます。
葬儀の希望
信仰上の理由による葬儀の形式の希望や、葬儀プランの希望(家族だけで出来るだけ質素に、など)などがあれば、エンディングノートに記載しておくことで、ご家族がご本人のご希望を汲んでくれます。
エンディングノートは遺言書と違って様式に決まりはありません。
自由に書いて大丈夫です。記録ですから。
その代わり、遺言書とは違いますので、エンディングノートに「財産は次男に全部」などと書いても有効にはなりません。
ですから、財産の承継、分け方、遺贈などについて残しておきたければ、やはり遺言書の作成が必要となる訳です。
エンディングノートを作って、ご自分の資産状況を客観的に把握、頭の中で整理して遺言書作成に取り掛かる、という流れも良いかもしれませんね。
専門家と任意後見契約をしていて、なおかつ当事務所で作成するような指図書、ライフプランのような書面を併せて作成している場合には、エンディングノートは必要ないかと思います。
(任意後見契約、指図書やライフプランについてはこちらのページから見て頂けます。)
